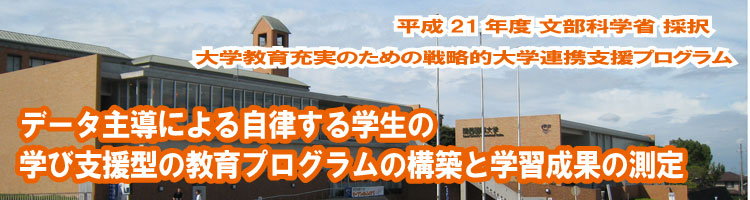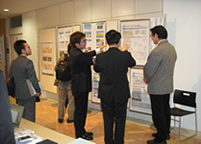教授過程・学習過程の構造化と学習成果
■ 12月2日(金) 15:00~17:30 ポスターセッション
 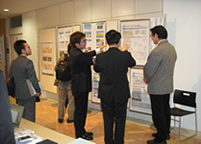
■ 12月3日(土) 10:00~16:40 シンポジウム
≪第1部≫
10:00~10:50 関西国際大学の教育改革の構造を振り返る
~学習支援・初年次教育からクラスター、学習支援型IR、
初年次サービスラーニング、ルーブリックの評価まで~
濱 名 篤 (関西国際大学 学長)
10:50~12:20 基調講演
「大学教育を通じた共通基盤の確立と個性の発揮」
榎 本 剛 氏 (文部科学省 高等教育局 企画官兼高等教育政策室長)
≪第2部≫
13:20~14:20 クラスター化とIRの取組概要と効果の検証
中 尾 茂 樹 (本学 学長補佐 教育学部教授)
藤 木 清 (本学 学長補佐 評価室長 人間科学部教授)
14:30~16:30 パネルディスカッション
「教授過程と学習過程におけるマネジメントの必要性」
コーディネータ 濱 名 篤 (関西国際大学 学長)
パネリスト 川嶋 太津夫 氏 (神戸大学 大学教育推進機構教授)
関田 一彦 氏 (創価大学 教育学部 児童教育学科教授)
森 朋子 氏 (島根大学 教育開発センター 准教授)
本学では、大学教育推進プログラムと戦略的大学連携支援プログラムが共に最終年度を迎えるにあたりまして、その成果と本学のこれまでの教育改革についてご報告する場を設けようということで、合同フォーラム開催の運びとなりました。当日は、関西地区はもちろん、関東や新潟、九州、沖縄と全国各地からも多数ご参加いただき、本学教職員を含め260名の参加者がありました。
第1部では、まず本学・濱名学長が「関西国際大学の教育改革の構造を振り返る」と題して、本学のこれまでの教育改革の取組について概観しました。続く基調講演では、ご多忙の中、文部科学省から榎本剛企画官においでいただき、「大学教育を通じた教育基盤の確立と個性の発揮」と題して、学生の入学動向、教育活動、進路の状況について多くのデータをご提示いただきました。また、今後の課題として大学の使命や特色、人材養成目的の明確化の重要性についてもお話しくださいました。
第2部では、クラスター化とIRの取組概要と効果の検証を、本学・中尾繁樹教授と藤木清教授により発表いたしました。続くパネルディスカッションは「教授課程と学習過程におけるマネジメントの必要性」というテーマのもと、3名の先生方にご登壇いただきました。パネリストの川嶋太津夫先生(神戸大学)には1991年以降の大学教育改革の流れから今後の学士課程教育の在り方をお話しいただきました。関田一彦先生(創価大学)には、創価大学の教育・学習活動支援センター(CETL)での取り組みを中心に、1つのセンターで教授課程と学習過程のマネジメントを行う利点と難しさについてご報告いただきました。森朋子先生(島根大学)には、島根大学の教育開発センターでのご報告を中心に大教センターが担う教育改革マネジメントの新しい形についてご提案いただきました
本学は全学生数が2000人に満たない小規模の大学です。さまざまな取組に次々と着手できるのも、実は大学の規模によるところが大きいようです。たとえば、大規模大学では学生一人一人に対してきめ細やかな指導やサポートをやりたくても、実現が難しいというのが実情です。しかし、本学では、小規模ゆえに実現が可能なのです。今後も本学が得た知見について情報発信し、大学教育の改革に本学が貢献できればと思います。
 
開催チラシ.pdf
|