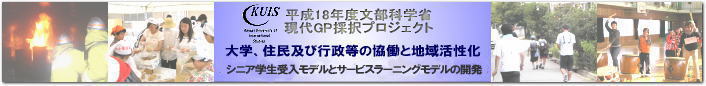
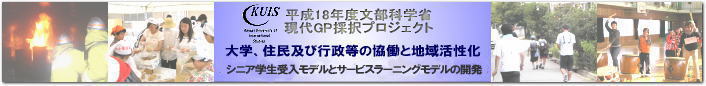 |
プロジェクト概要 (全体図)1 採択された取組「大学、住民及び行政等の協働と地域活性化 人口減少下の少子高齢社会である21世紀は、前世紀に形作られた多くの役割の転換が求められる社会です。社会の変化・要請を踏まえて、地元自治体・住民と協働して、新しい地域社会をめざし、「大学、住民及び行政との協働による地域活性化プロジェクト」をスタートさせました。 取組は、住民・学生・大学および行政が協働して、学生消防隊創設、防災・防犯マップの作成、子育て支援等地域の安全・安心の確保 、住民活動の相互支援、シニアの持つ知 識・技能の共有などによる地域の活性化をめざすものです。 地域に暮らす様々な人たち及び機関の参画によるこれらの活動を通して、大学における「教育力の向上」や団塊世代等の受け入れ・セカンドライフへの取組支援を行います。 2 取組のポイント 3 具体的取組例(今後の予定)① 地域の安全・安心確保 ② 地域の活性化   
隣接する兵庫県広域防災センターには消防学校と世界最大の実大三次元震動破壊実験施設がある 広域防災センターでの模擬訓練 子どもの目線から防災マップ作成
実現のための手法 これらの取組を行う中で、学生一人ひとりの個性を大切に、本学の教育目標の実現を図ります。 1 サービスラーニングの手法の開発・定着 サービスラーニングとはアメリカで行われている教育手法で、学生が地域の課題の解決に向けて、地域の住民とともに解決に向け取り組む手法です。 【サービスラーニングのプログラムイメージ】 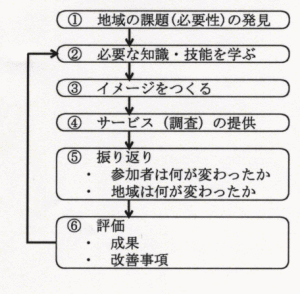
サービスラーニングの実践に当たっては、参加する学生自身がその取組を十分理解できるか、教員がそのように支援できるかがポイントとなる。 2 ラーニングコミュニティ 本学の特徴である少人数ゼミの特徴を活かし、その中をさらに分けて4〜5人のグループを作り、学習に取り組みます。 3 プロジェクトゼミ ゼミを単位に、あるいはゼミ同士が協働して、課題を設定して課題の解決のための具体的取組を行うことで、授業で獲得した「専門知識」検証します。
【図1】本学におけるサービスラーニングの位置づけ ※本学では地域活性化のために、平成17年11月に三木市との間で「連携協力に関する協定」を締結しました。 また、隣接する兵庫県広域防災センターとも、平成18年10月に「防災に関する連携支援協定」を締結し、連携を図っています。 本プログラムの到達目標1 教育力の向上サービスラーニング、サービスラーニングコミュニティ、プロジェクトゼミ、シニア学生や留学生等との交流など多様な方法の工夫により、教育力の向上を図ります。 2 シニア学生の支援団塊世代の大量退職等の中、地域への貢献、新たなビジネスシーンの創造、人生の棚卸し等を通じ、セカンドライフのスタートを支援します。 3 地域の活性化
|
||||||||||
|
トップページ | 現代GPについて | プロジェクト概要 | プロジェクト一覧 | 具体的な取組 Kansai University of International Studies (C) 2006 All copyrights reserved. |
||||||||||