高等教育研究開発センター
高等教育研究開発センターの役割
高等教育のユニバーサル化とともに、学生の学習目的や学力・意欲などが急速に多様化しています。このような状況において、学生の高等学校から大学への円滑な「移行」を促進することが重要となっています。そこで本学では、学生にとって重要な「移行期」にあたる「初年次」(大学生活の1年目)の教育に力を入れ、高等学校から大学への円滑な移行を促進する、さまざまな教育プログラムを実施しています。
また、社会の変化とともに、大学は四年間の教育を通して、「学士」という学位を与えるに値する教育内容と質を保持しているかが問われるようになりました。そこでは、教育デザインと有効なメディア活用のための取り組みが求められています。本学では、教育の改善と質の向上を目指し、学術的かつ実証的な研究と、それにもとづいた教育プログラムの設計・開発を行なっています。

同センターの活動
本センターは、教育開発部門、初年次教育部門、ICT教育部門、教養教育部門、外国語教育部門、教材開発部門の6部門からなります。教育開発部門では、学士課程教育における質保証に関する研究と教育プログラムの開発、教育の質を評価 ・向上させるための基準や方法論の確立に取り組んでいます。初年次教育部門では、学生の高等学校から大学への円滑な移行を促進するための「初年次教育」に関する研究と教育プログラムの開発とマネジメントを行っています。ICT教育部門では、ICTを活用した教育の研究および開発を行うと共に、データサイエンスのカリキュラムを構築し、問題解決能力の向上を目指します。教養教育部門と外国語教育部門では、全学共通の基礎教育の目標を設定し、その内容や教授法、運営・実施方法について検討しています。特に、外国語教育においては、コミュニケーション能力の向上、異文化理解、学術的基礎の構築を目指した教育プログラムの開発を行っています。2025年度より新設される教材開発部門では、オンデマンド教材作成のサポートやインストラクションを通じて、有効な教材開発を目指します。

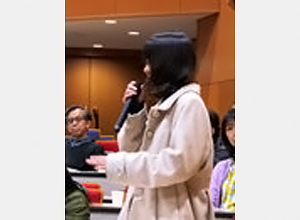
また、本センターは、神戸山手・尼崎・三木3キャンパスの教職員が一堂に会する年間に計5日間のPD(Professional Development:大学の教職員の専門性を強調し、教員研修(FD)、職員研修(SD)等をカバーし、教職員の専門的能力開発を目指した組織的な取り組みの総称)研修会を開催し、組織的な教育力の向上に寄与しています。内容は、「学期の主題」に基づく科目の統合化、アクティブ・ラーニングの推進、シラバスの改善、ルーブリックの活用、eポートフォリオの充実、各種データの分析、優れた教育実践の共有、海外の先進的取り組みに学ぶことからオフキャンパスプログラムの充実まで、多岐に渡ります。教職員の研修会ではありながら、毎回学生の参加を促していることも、本学PD研修会の特筆すべき点です。
スタッフ
| 高等教育研究開発センター長 | 上村 和美(経営学部 教授) |
|---|---|
| 教育開発部門長 | 椋田 善之(教育学部 准教授) |
| 初年次教育部門長 | 田中 亜裕子(心理学部 准教授) |
| ICT教育部門長 | 章 志華(社会学部 教授) |
| 教養教育部門長 | 谷口 一也(教育学部 准教授) |
| 外国語教育部門長 | 横山 雅彦(国際コミュニケーション学部 教授) |
| 教材開発部門長 ※2025年度より新設 |
福田 美誉(高等教育研究開発センター付) |
同センターの歴史
| 1998年4月 | 本学開学と同時に高等教育研究所を開設。 |
|---|---|
| 1999年4月 | 本学初の初年次教育プログラムとして「講義の攻略法」「ノートテーキングの方法」を、学習支援センターのショートプログラムとして開講。 |
| 2000年4月 | 「講義の攻略法」「ノートテーキングの方法」を基礎に、全学基本教育科目として「学習技術」を開講。 |
| 2002年4月 | 「学習技術」の教科書『知へのステップ』をくろしお出版から刊行。同年度の全国大学生協の売上第13位。 |
| 2004年4月 | 高等教育開発センターを開設。 |
| 2004年7月 | 「大学のユニバーサル化と学習支援の取組」で文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」に採択される。 |
| 2004年8月 | 初年次教育研究開発センターを開設。 |
| 2005年4月 | 全学共通科目「キャリアプランニング」を開講。 |
| 2006年3月 | テキスト「知のワークブック」をくろしお出版から刊行。『日本創造学会』著作賞受賞。 |
| 2006年7月 | 「初年次教育の総合化と学士課程教育への展開」で文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」に採択される。 |
| 2008年4月 | 高等教育開発センターと初年次教育研究開発センターを統合し、高等教育研究開発センターとする。 |
| 2009年4月 | 「仕事とキャリア形成I」、「仕事とキャリア形成II」を新規開講。 |
| 2009年7月 | 「出遅れない就職活動へ誘うための重層的支援」で文部科学省「学生支援推進プログラム」に採択される。 |
| 2011年4月 | 高等教育研究開発センターにキャリア教育部門を置く。 テキスト「夢をかなえるキャリアデザイン」をくろしお出版から刊行。 |
| 2012年4月 | 「キャリアプランニング」を発展解消し、「初年次セミナー」を新規開講。 |
| 2012年4月 | 文部科学省平成24年度「大学間連携共同教育推進事業」に採択(3ヶ年)され、高等教育研究開発センター所管の取組としてスタート。 |
| 2014年4月 | キャリア教育部門をキャリア教育委員会として独立させる。 |
| 2015年4月 | 文部科学省の「大学教育再生加速プログラム」(Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP)に、テーマⅠ(アクティブ・ラーニング)+テーマⅡ(学修成果の可視化)の複合型で採択され、人間科学部を中心として取組をスタート。 |
| 2015年4月 | 「学期の主題」に基づく科目統合の取組を全学的に開始する。 |
| 2016年4月 | 「ラーニングルートマップ」の取組を全学的に開始する。 |
| 2018年3月 | 到達確認試験の実施。 |
| 2018年4月 | 高等教育研究開発センターにメディア教育部門を置くとともに、インストラクショナルデザイン(ID)の知見や、ICTの有効活用を授業設計に役立ててもらうことを目的として、教員支援サイトを立ち上げる。 5学部5学科体制へ向けて「学修フローチャート」の取組を全学的に開始する。 |
本学PD研修会の内容
2024年度
年間テーマ:「教職員が理解しておくべき多様性への対応について」
| 回 | 日程 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1回 |
8月26日(月)/ 27日(火) |
尼崎 | ●テーマ「高等教育機関における学生支援~合理的配慮とは何をどこまですることなのか?をもう一度考える」 (筑波大学 ヒューマンエンパワーメント推進局 准教授・舩越 高樹先生) ●増加する留学生についての理解共有と課題整理 ●教養教育改革の進捗状況について ●理解共有(本学の教育改革の取り組み解説) ●オンライン・オンデマンド授業の戦略的導入
●テーマ「教育現場のAI活用:理解から実践へのファーストステップ」 (創価大学 学士課程教育機構 助教・高橋 博美先生) ●実際の文脈で生成AIを活用する演習 |
| 第2回 | 9月19日(木) | 尼崎 | ●留学生の卒業後の進路状況・進路希望状況等について ●「初年次におけるラーニングコミュニティの検討 ― 1年生の適応促進と学業面での成功を目指して」 ●情報共有とロールプレイ
「プロンプトの書き方と授業準備支援」 |
| 第3回 |
2月20日(木)/ 21日(金) |
尼崎 | ●学修状況に関する現状報告 ●LC(ラーニングコミュニティ)の取り組み
|
2023年度
年間テーマ:「学生の多様化の中の教育 ―「学生が学べる」 環境と機会を整える」
| 回 | 日程 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1回 |
8月24日(木)/ 25日(金) |
尼崎 | ●学生指導・支援における「多様な場面」への対応
(リクルート 総研所長/本学客員准教授 森崎 晃 氏) ●学科ワーク➁:タイプ別の科目割り当ての検討と整理 ●双方向性の確立、評価の多元化と ツールの活用について解説 ●個人ワーク:担当授業1コマをオンデマンド化する実習 |
| 第2回 | 9月21日(木) | 尼崎 | ●学習者本位の学びとなるような評価の方法について考える
●学科ワーク:2024年度を睨んで、学科のカリキュラム運営において戦略的にオンデマンド型授業を取り入れるための検討と課題要素と対応方策の整理 |
| 第3回 |
2月20日(火)/ 21日(水) |
尼崎 | ●2024年度のオンデマンド授業運用の準備確認 オンデマンドで学習ができる授業設計・教材・学習サポート体制・評価・フィードバックの方法等の確認 ほか ●2024年度キャリア科目の変更点について ほか ●インクルーシブ支援委員会からの情報共有 ●ChatGPTなどの生成AIの「業務活用」 ・・・事務局・学科業務で使うことを考える ●ChatGPTなどの生成AIの「教育活用」 ・・・教育場面・学習場面で使うことを考える ●シラバス確認ワーク |
2022年度
年間テーマ:「「学生が学べる」 環境と機会を整える ― 学生の多様化への対応」
| 回 | 日程 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1回 |
8月18日(木)/ 19日(金) |
尼崎 | ●「学び」の現状報告
●テーマ「多様化する学生への大学としての支援」 (心理学部 准教授・松井 幸太先生) ●テーマ「学生理解と危機管理&危機対応の基本について」 (教育学部 教授・百瀬 和夫先生) ●ワーク:授業内外での学生対応における個々の体験について共有し議論する ●オンデマンド授業に関する概要説明-本学で実践するための理解共有 ●テーマ「オンデマンド授業に関する企業の取り組み事例紹介」 (NTT ドコモ イノベーション統括部 課長 安部 孝太郎氏 ドコモgacco CLO 南 圭氏) ●テーマ 「共愛学園前橋国際大学でのオンデマンド授業の設計と実践」 (共愛学園前橋国際大学 国際社会学部 学部長・村山 賢哉教授) ●講習:オンデマンド授業を作ってみる① 簡単に始められる、教材コンテンツ制作方法のご紹介 ●ワーク:オンデマンド授業を作ってみる② 早速、自分のネタで作ってみるワーク ほか |
| 第2回 | 9月15日(木) | 尼崎 | ●テーマ 「個別最適化学習とカリキュラム・マネジメント」 (関西国際大学 客員教授 神戸山手女子中学校高等学校 校長・平井 正朗氏) ●テーマ「電子教科書の利用事例について」 (丸善雄松堂株式会社企画開発統括部 電子ソリューション開発センター・田端 勇氏) ●テーマ「オンライン授業用教材における著作物の使い方」 (金沢大学学術メディア創成センター助教・森 祥寛先生) ●講習:「授業目的公衆送信補償金制度と、オンライン教材の有効活用について」 ●シラバス作成上の注意点を確認 -学生のためのシラバスづくり- ほか |
| 第3回 |
2月20日(月)/ 21日(火) |
尼崎 | ●テーマ 「マーケットから見た関西国際大学の整理~大学を取り巻く環境の変化から~」 (リクルート 小林 浩氏) 対談 リクルート 小林 浩 氏 × 濱名 篤 学長 ●「学生の成長実感の向上に向けて-CP 評価の観点から-」 ●「本学における障がい学生支援の対応について ー学生の人権問題も含めてー」(山下泰生 副学長) ●「次年度アドバイザー教員の役割の見直しに向けて」(濱名陽子 副学長) ●情報共有とワーク:2023年度からの「アドバイザー教員の役割」を熟知する ●情報共有とワーク:2023年度の初年次教育改革 ●情報共有とワーク:担当科目での学生の学習活動をアクティブにするための方策 ●講習とワーク:担当科目で使うICT ツール活用方法の習熟 ●ワーク:2023年度科目の授業計画(シラバス)をチェック ●解説:「展開力事業を契機とするCOIL 型協働教育の推進と外部リソースの活用」(芦沢真五 副学長) |
2021年度
年間テーマ:オンラインでも「学生が学べる」環境を整える
| 回 | 日程 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1回 |
8月19日(木)/ 20日(金) |
尼崎 | ●本学の教育システムの特徴について解説 ●学生の状況に関するデータ共有と分析
|
| 第2回 | 9月16日(木) | 尼崎 | ●テーマ 「内なる多様化への対応に向けて」 (濱名 篤 学長) ●8月PDからの継続
(実践女子大学 学長補佐・教授 深澤晶久氏) ●PBL手法の活用アイデア ディスカッション
|
| 第3回 |
2月17日(木)/ 18日(金) |
尼崎 | ●テーマ 「教育課程と質保証」 (大阪大学 高等教育・入試研究開発センター教授/本学院評議員 川嶋太津夫氏) ●報告 「学生の学びの状況」 ●テーマ「教育DXと『未来の教室』の姿を考える」 (経済産業省サービス政策課長・教育産業室長 浅野 大介氏) ●報告とワーク「学びの仕組み」における3つの教育プログラムを「連携」させる
●教育DXによる新しいシステム・機能の利用説明会等のご案内 |
2020年度
年間テーマ:「2021年度 3キャンパス新体制スタートのための教育活動アセスメント」
| 回 | 日程 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1回 |
8月20日(木)/ 21日(金) |
尼崎 | ●本年度着任された教職員向けオリエンテーション ●教育・学習活動におけるコロナ対応から課題提起ならびに学科の課題抽出ワーク ●「科学研究費補助金の申請に当たって」(愛知教育大学・後藤博明先生講演) ●「コロナへの対応を教授学習パラダイム転換の機会に」(桐蔭学園理事長・溝上慎一先生講演) ●【パラレルセッション】 ①遠隔で授業を受けた学生からの声 ②遠隔・対面授業における1年生への対応・支援(リフレクション面談を想定して) ③本学学生の出口に関わる課題 ●学科別問題点の整理と共有 ●秋学期・2021年度を睨んだ授業デザイン検討ワーク ①-1オンラインでも学べる授業を設計するための教訓を引き出す ①-2オンラインでの学習指導におけるtipsと問題点を共有する ②学科の学修フローチャートを授業デザインの観点で再チェックする |
| 第2回 | 9月17日(木) | 尼崎 | ●秋学期に向けて:学生指導における各システムの活用方法 ●「教員による学生へのキャリアアドバイジング ~主体性を育むキャリア教育と学生支援とのつながりを目指して~」(実践女子大学・深澤晶久先生講演) ●8月PD学科ワーク「問題・原因・対応方策」に関する進捗プレゼン ●学習者中心の学びを考える:リフレクションの再確認ワーク ~メタ認知力の観点からみたアドバイジングの検討~ ●1年生の学びを支えるための学科ディスカッション ~秋学期リフレクション面談の検討~ |
| 第3回 |
2月18日(木)/ 19日(金) |
尼崎 | ●次年度着任予定の教員向けオリエンテーション ●2020年度の教育と学習の総括/今後の展望 ●個別最適学習と協働学習を両立させた新たな教育へ ●「重要科目に焦点化したパフォーマンス評価による学習成果の可視化」(京都大学・松下佳代先生) ●学科ワーク ①ゼミを軸とした「現実の文脈に近い学習活動と評価」のための学科・学年・学期ごとの関連科目の抽出 ②学科の課題と対応方策の検討 ③学科発表 ●教育のデジタル化をニューノーマルに:オンライン授業のススメ ●シラバス作成のための授業デザイン確認 |
2019年度
年間テーマ:「『重層構造の組織的な教育の仕組み』の具現化に向けて」
| 回 | 日程 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1回 |
8月21日(水)/ 22日(木) |
尼崎 | ●本年度着任教職員向けオリエンテーション ●「将来予想が困難な時代における学びの実践にむけて」「学修成果の可視化に向けた評価方法の理解-コモンルーブリックのワーク及びeポートフォリオの活用について-」 ●「学習者の思考を刺激する発問」(愛媛大学・中井俊樹先生講演) ●「各学部の『考えさせる教育』への質的転換を目指したワークー経験学習と授業のシナジー効果を高めるためにー」(「生徒指導論」科目の実践から/初年次教育の実践から/経験学習の実践から)「各学部のゼミ(総合演習)科目における『思考力を深める』ためのテーマ設定ワーク」 ●コース選択制プログラム ①ルーブリック・モデレーション入門コース ②教育、研究指導に生かす情報検索リテラシーコース、ウェブクラス・eポートフォリオ等のICTを活用した授業デザインコース(基礎) |
| 第2回 | 9月20日(金) | 尼崎 | ●「質問会議を活用した授業の紹介と教員間の同僚性の向上について」(創価大学・望月雅光先生講演) ●ゼミ科目における「思考力を深める」ための学習目標・テーマ設定ワーク(8月PDの続き) |
| 第3回 |
2月13日(木)/ 14日(金) |
尼崎 | ●「本学の組織的な教育の充実に向けた全学的な課題」「本学のアセスメントポリシーに基づいた教育改革の課題について」 ●「アクティブ・ラーニングとリーダーシップ教育」(早稲田大学・日向野幹也先生講演) ●「課題発見力・課題解決力の涵養に向けた共愛学園前橋国際大学の取組」(共愛学園前橋国際大学・大森昭生学長講演) ●「大学教育再生加速プログラム(AP事業)における課題解決型インターシップの取組みと課題」 ●「科目間連携を踏まえたゼミ改革ワーク」「シラバス作成に関する共有ワーク |
2018年度
8月テーマ:「『専門的知識・活用力』を身につけるために必要な教育方法とは何か」
9月テーマ:「『専門的知識・活用力』『問題発見・解決力』を身につけるために必要な教育方法とは何か」
2月テーマ:「次年度の5学部体制に向けたカリキュラムの履修指導の準備はできているか」
| 回 | 日程 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1回 |
8月22日(水)/ 23日(木) |
尼崎 | ●本年度着任教職員向けオリエンテーション ●「2040年に向けた高等教育の将来構想と本学が取り組むこと」「2019年度からの新学部体制の方向性について」「IRデータに基づく各学部の学修成果の可視化について」「学修成果の可視化に向けて‐教育方法、成績評価の自己点検‐」 ●「PBLの授業設計に向けて」(同志社大学・山田和人先生講演) ●「新学部カリキュラム・マップ作成のワークショップ」 ①②(大阪大学・佐藤浩章先生講演・ワークショップ)「新学部のカリキュラム・マップツアー」(ポスターセッション)学部代表者によるカリキュラム・マップ発表 |
| 第2回 | 9月20日(木) | 三木 | ●「現行の教育方法、教育評価の課題と新学部に向けた改善プランについて(5学科)」「パネルディスカッション形式による質疑」 ●「シラバスチェックの自己点検Ⅰ:チェックシートで点検・修正ワーク」「同Ⅱ:ICT活用の観点で修正ワーク」 ●「ケースメソッド教授法の共有ワーク」 |
| 第3回 |
2月14日(木)/ 15日(金) |
尼崎 | ●「中教審グランドデザイン答申後の行方」「IRデータを活用した本学の自己点検評価」 ●「新学部の学修フローチャートに関するポスターセッション~ギャラリーツアー及び各新学部代表者によるプレゼンテーション~」「新学部の学修フローチャートを踏まえた履修指導のシミュレーション」 ●「学士力の質保証-『卒業研究』の実質化に向けた授業設計の見直し-」 ●「アカデミック・ライティングを通していかに学生の『思考を鍛える』のか」(桜美林大学・井下千以子先生講演) ●「学生の視点に立ったシラバス作成の自己点検ワーク」 |






