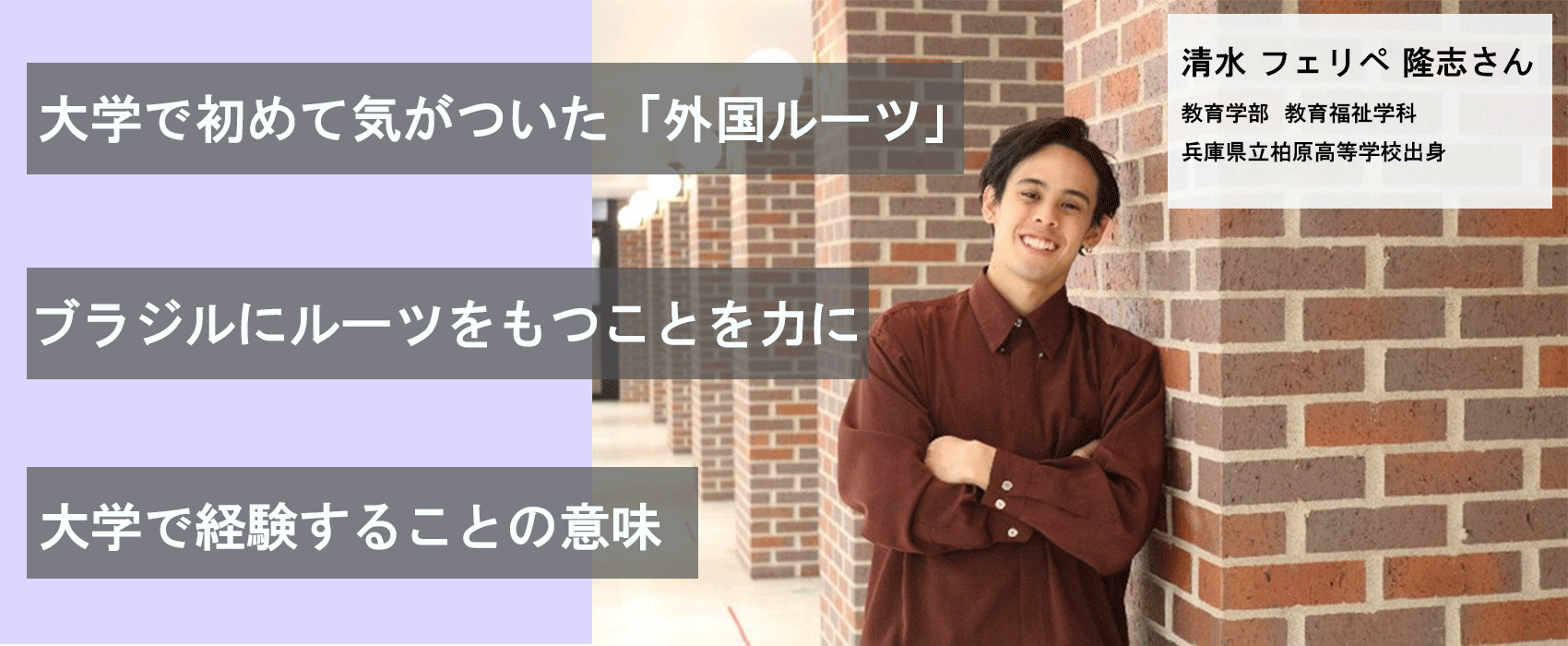
在学生の成長ストーリー (大学で初めて気がついた「外国ルーツ」)
外国にルーツをもつ学生
1990年の改正入管法以降、日本で生活する外国人は急増するようになりました。それから30年。日本の教育現場において、両親のいずれかが外国出身である子どもは日常のものとなりつつあります。こうした外国に「つながり」や「ルーツ」をもつ大学生を「外国ルーツの学生」として、本学は位置付けています。
「外国ルーツの学生」といってもバックグラウンドは千差万別です。出身国の違い。外国生まれである場合もあれば、日本生まれの場合もあります。共通している点は、日本での学校経験を有することです。
これまでの大学は日本人の学生が多数を占め、留学生が若干名という構成にありました。近年、日本人と留学生の構成比率も変化していますが、外国ルーツの学生も大学に進学するようになっています。外国ルーツの学生は、日本人学生や留学生とは違った可能性を有する学生です。こうした学生を積極的に受け入れるため、関西国際大学では外国ルーツ特別入試を実施しています。
今回のインタビューでは、教育学部で学ぶ外国ルーツの学生を紹介します。
日本とブラジルというルーツ
清水フェリペ隆志です。父と母はブラジル人で、日本にやってきました。私自身はブラジルにルーツがありますが、日本で生まれました。1度だけ、ブラジルに行ったことがありますが、子どもの頃だったのであまり覚えていません。
私にとってブラジルは母国・・・という表現もあるのですが、「家」というイメージが強いです。生まれも育ちも日本なので、母国は日本です。自分にとって第2の「家」です。祖父母もブラジルにいますし。いつかは、ブラジルを第2の活躍できる場所にしたいです。
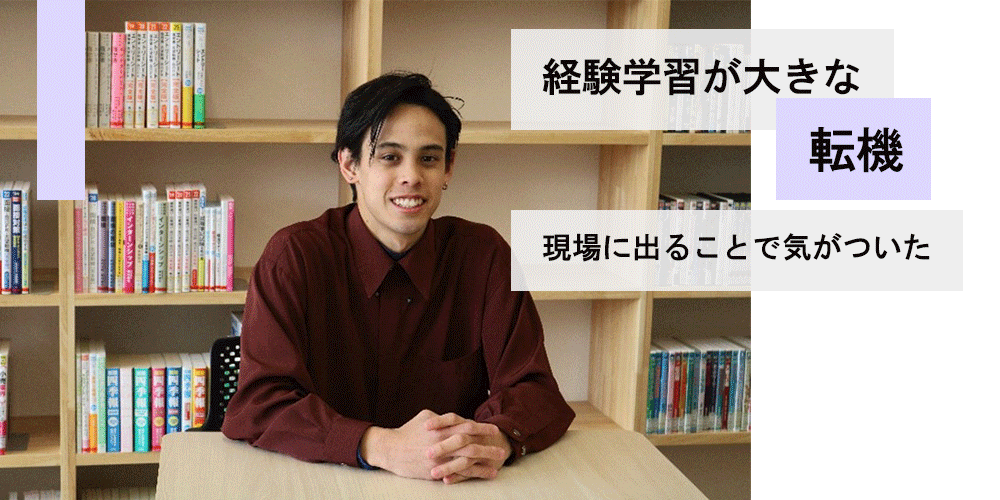
日本での生活とルーツ
両親は日本で働くためにやってきました。両親のように、日本にやってきたブラジル人は多くいます。私の親類も日本で生活しています。両親は様々な仕事に携わってきました。
家庭内ではポルトガル語を使うことが多いのですが、学校などでは日本語です。両親も日本語を一生懸命勉強していましたが、専門的な話しなどは私が通訳をすることもあります。仕事上でも苦労することが多かったようです。そうした家族の大変さについては、ようやくわかるようになってきました。
というのも、私自身は小学校や中学校の頃に苦労することがありませんでした。幼少期から日本で生活してきました。友人も多かった。先生も配慮的でした。むしろ、外国人扱いされることに不満を感じることさえありました。「僕はできるのに、どうしてできないかのように扱うのだろう」。周囲に外国ルーツの子どもはほとんどいなかった。差別やいじめとは無縁でした。「外国人扱い」そのものに違和感を抱いていました。
大学での経験(外国ルーツの意味を考える)
大学に入学してからも「教師になりたい」という展望はもっていましたが、自分が外国ルーツであると意識することはほとんどありませんでした。「外国にルーツのある日本人」という表現になるでしょうか。別に生活上で嫌なことはなかったし、そういうものと思っていました。日本語でコミュニケーションできて、学業に向き合うこともできたので。
転機となったのは「グローバルスタディ」という授業です。経験学習という枠組みで、国内・国外のさまざまな現場に出ていきます。私は外国ルーツの子どもの学習支援プログラムに参加しました。NPO法人神戸定住外国人支援センターさんがおこなっている学習支援に2か月間関わりながら、様々なことを考えました。外国ルーツの小学生、中学生が放課後に宿題や日本語に取り組んでいます。こうした子どもたちの学習を支えるという内容です。
このプログラムを担当している先生と授業期間内にいろいろな議論をします。例えば、「外国人の子どもたちが日本で一生懸命勉強することに問題はないのか」など。私は「外国から来た子どもが勉強するのは当たり前ではないか」と考えました。ですが、「日本にやってきて間もない子どもが苦労しなければならないのはなぜなのだろうか」と考えることにもなりました。勉強に困らないために「なんとかしてあげたい」という気持ちがある一方で、子どもたちが大きな負担に晒されていることに気がつきました。
また、子どもたちが自分のルーツに対してポジティブに感じているのか、わからなくなりました。子どもたちが置かれた環境は、自分のルーツを誇らしいと思えるような状況にないように見えました。私自身も日本国籍を取って、日本名で教師になるイメージをもっていました。それでいいのだろうか、と考えるようになりました。
同じ外国ルーツの学生との交流
こうした学習支援の経験を経て、NPO法人神戸定住外国人支援センターさんが主宰する「外国ルーツの学生交流会」に参加しました。そこではじめて「自分が悩んでいることを話せる」経験を得ました。外国ルーツ学生といっても事情は様々です。悩んでいることにも違いがあります。ですが、同じルーツをもつから話せることがありました。
私の母語は日本語ですが、第2の言語としてポルトガル語は使える。けれどそれらについて深く考えることはこれまでありませんでした。ですが、同じような仲間と話していると外国ルーツだからできることもあるのではないかと考えるようになってきました。例えば「共生社会」が語られるとき、私たちの言葉がそこに届いているのだろうか。合宿を通じて語り合うなかで問題を明確にしていきました。この1月には行政関係者をはじめ、多くのアクターとワークショップをおこなうことができました。これをきっかけに、難しいことはありますが、外国ルーツの若者が語り合える場づくりをしていきたいと考えています。
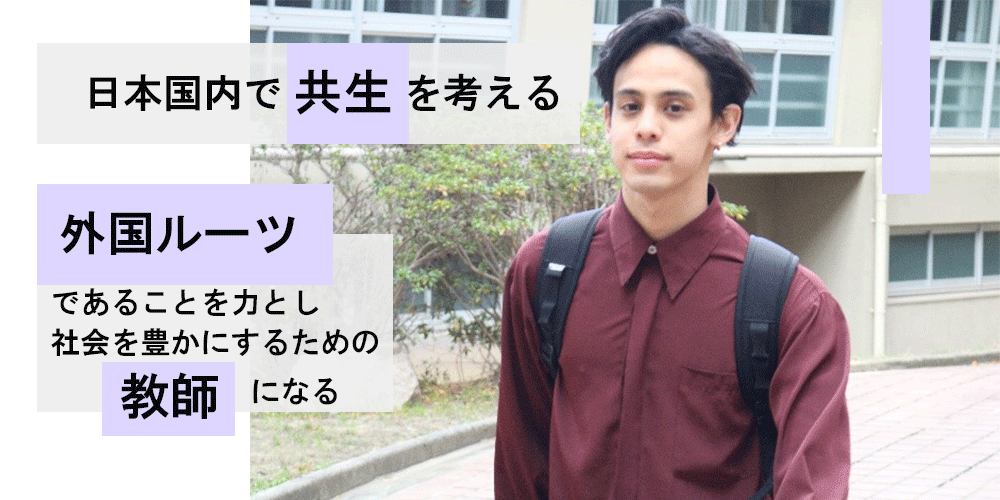
自分のルーツを社会で役立てたい
大学での学びを通じて、外国ルーツの子どもたちにとって「ルーツ」はどのような意味があるだろうか考えるようになりました。外国ルーツだから外国ルーツを意識しなければならないということではありません。ですが、外国ルーツをもつということで出来ることがあるはず。私にとって自分のルーツが選択肢であったように、子どもたちに選択肢を与えられる教師になりたいと思っています。そのうえで、自分のようにルーツがある教師がいれば、外国ルーツの子どもだけでなく、日本人の子どもにとっても学びがあるのではないかと考えています。私自身は、同じブラジルルーツをもつ子どもが多い地域で教員になるつもりです。
大学でも私たちのような外国ルーツについて理解が広がっていけば良いと考えています。外国ルーツの存在が知られていないこともあるでしょう。外国ルーツの子どもが困っているだけのように一面的に理解されていると思っています。外国ルーツといっても様々です。そうした学生がもっと活躍できる場ができて欲しいです。
【語り:教育学部3年 清水 フェリペ 隆志さん 聞き手:社会学部教員 山本晃輔】