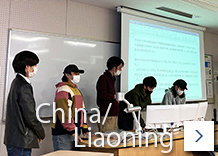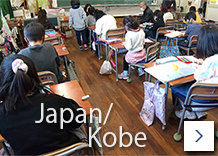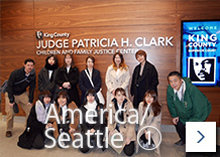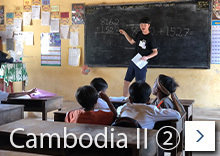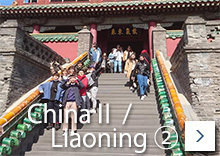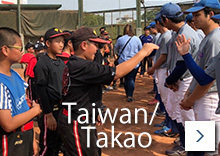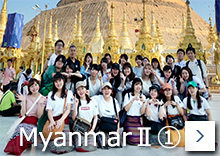国際交流・海外プログラム 海外プログラム
グローバルスタディ
グローバルスタディとは
世界がキャンパス!多彩な海外体験プログラム
すべての学部で海外体験のチャンスがあります
これまで以上に世界の人々との相互理解を深め、関係を強化していくことが必要な時代となってきています。本学では2011年から、国際的な視野で物事を考える力を身につけるために、世界とつながる「体験」を中心とした学習プログラム「グローバルスタディ」を実施しています。異なる文化や考えを持った人々と出会い、交流することで、多様な価値観や文化的背景を理解する力を養います。
本学のすべての学部の学生がグローバルスタディに参加することが可能です。

プログラム紹介
グローバルスタディには次のプログラムスタイルがあります。
海外渡航プログラム
実際に海外に行き、調査活動や社会貢献活動などを行います。
国内プログラム
- 日本国内の在日外国人コミュニティでの活動を通じて、自分の生活圏における多文化共生について深く考えます。
- 海外協定校からの受入留学生と交流しながら、国内で視察・調査活動などを共同で行います。
活動報告一覧
2025年度
| 種類 | テーマ | 国/地域・協力先 | 様子 |
|---|---|---|---|
| 世界展開力 14日間 |
産学官連携ベンチャー・エコ・システム創成による起業家育成カリキュラムの展開 | オーストラリア/シドニー ウェスタンシドニー大学 |
|
| 海外渡航プログラム 6日間 |
「少子化先進国」韓国から学ぶ今後の観光戦略と、インバウンド観光客向け日韓協業の可能性探求」 | 韓国/ソウル 祥明大学校 仁徳大学 |
|
| 海外渡航プログラム 17日間 |
マレーシアにおける気候変動・災害対策フィールドワークと防災教育の実践 | マレーシア ウタラマレーシア大学 |
|
| 国内 | 日本における外国にルーツをもつ子どもたちの現状と課題について考える |
日本 尼崎市内小学校 |
|
| 海外コーオプ プログラム |
海外での就業体験で、将来のビジョンを明確に | 中国 青島濱海学院 |
|
| 交換留学 | 多様なグローカル人材育成に向けた交換留学生派遣プログラム | 韓国 祥明大学校 |
2024年度
2025年5月31日(土)に尼崎キャンパスで、2024年度冬学期グローバルスタディ全体報告会が開催されました。各テーマ毎に、写真、フローチャートはじめ多様な手法を用いて作成されたポスターに基づく報告・発表10分、質疑応答10分、評価5分のセッションが計4回実施されました。
| 2024年度冬報告会 |
| 2024年度夏報告会 |