ハロウィンの飾りをあちこちで見かけるようになりました。ハロウィンと言えば、カボチャのオレンジ色の飾りが多いですね。
オレンジ色は、このハロウィンの飾りや、果物のオレンジ、ミカンに代表される色ですが、英語では猫の毛色にも使います。orange cat=オレンジ色の猫、とはどんな猫だと思いますか?ミカンの実のような色をした猫は漫画やイラストでは見かけても、実際には見かけませんよね。日本語では茶色の猫のことです。
英語の方が日本語よりも少し幅広く、茶色を含めた色をorange(オレンジ)で表します。
同じように日本語では「青」が「緑色」も含んで使われます。「青々とした葉」などと表現しますが、葉っぱは普通「緑色」です。信号も「青信号」と呼ばれていますが実際の色は「緑色」ですよね。小さい時になぜ「緑信号」と呼ばないのか、不思議に思いませんでしたか?英語では、青信号は見た通りの "green"を使って表現します。
実は、古代の日本語は、赤青黒白という4つの単語で色を表していました。したがって、「青」が緑色も含めて使われていたのです。そのため今でも実際は緑なのに「青」を使う表現が多く残っているのです。
同じ色を表していると思っても、言語によって差があるので、他の外国語を勉強する機会があれば調べてみてください。
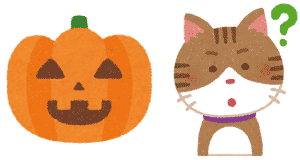
国際コミュニケーション学部 英語コミュニケーション学科 教授 片山 真理






