ウソ発見機って、どんな機械か知っていますか。「あなたが、現金を盗みましたか」と聞かれて、ドキッとしたら反応する、というようなイメージでウソ発見機を考えてはいませんか? 多くの一般市民は、一生涯にわたって、犯罪に手を染めることなんてほとんどないと思います。しかし、自分は関係ないのに、犯罪の疑いをかけられてしまうというようなことが、「絶対にない」とは限りません。
たとえば、こんな場面を考えてみましょう。
学校の帰り、あなたは、たまたま道ばたに落ちていた財布を1個、拾ったとします。中を見ると、クレジットカードや診察券などが入っていたので、落とし主が困っているであろうと心配して、すぐに最寄りの交番に届けたとします。
あなたは親切なことをしたと思って、ちょっといい気分になります。

ところが、1週間ほど後になって、あなたの元に警察から、こんな電話が入ります。
「このたびは、財布を届けてくださって有り難うございます。落とし主はすぐに見つかり、財布を返そうとしましたが、財布に入っていたお金が、無くしたときよりもちょっと少ないと落とし主が言っているのですよ。なにか、知りませんか?」。警察官の言い方はいかにもあなたが届ける前に、お金を少し抜き取ったように疑っているように聞こえます。そして、最後にこう言います。「あなたが犯人でないとおっしゃるなら、ウソ発見の検査を受けてもらえませんか?大丈夫、無実なら、反応しませんから・・・」。
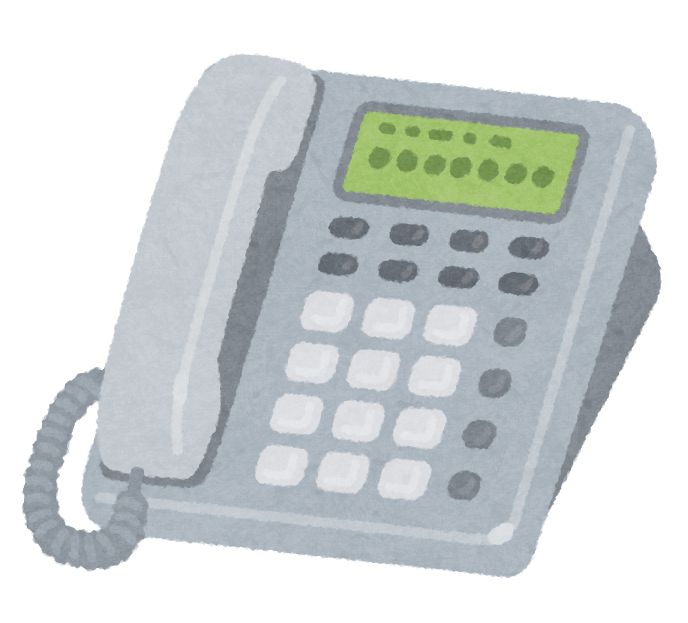
警察官の言い方はやさしいようにも聞こえるけど、犯人ならウソ発見機にかければ一発でばれてしまうぞという、脅かしにもとれるようないい方です。自分はもちろん、お金を盗んではいないけど、ちょっと神経質で動揺しやすいこともあるから、反応してしまったらどうしようと考えつつ、断ると余計に疑われそうなので、やむなく検査を受けることにします。
そして、翌日、警察署に向かうと、取調室に案内され、検査を受ける承諾書を書かされたあと、電極などをつけられて、いよいよ検査が始まります。
あなたは、てっきり、「お金を盗んだのはあなたですか」とズバリ、聞かれるのではと思って、おどおどしていました。

ところが、検査者の最初の質問は意外にも、「財布から抜き取られた金額はいくらか、尋ねます」というのものでした。あなたは咄嗟に「そんなこと知りませんよ」といいましたが、検査者は「知らなければ、知らないと答えてくれたら、いいのですよ」と素っ気なくいいます。そして、機械を動かしながら「1万円でしたか」「2万円でしたか」「3万円でしたか」「4万円でしたか」「5万円でしたか」と20秒おきに聞いてきます。
あなたはもちろん、どの質問にも「知りません」と答えます。お金を抜き取ってはいない人間であれば当然です。
実は、先ほどの5つの質問の中に、落とし主が主張する、抜き取られた被害金額(正解)が含まれているのです。そして、犯人であれば、正解がどれかを知っているので、他とは違う反応が出るというのがこの検査の原理です。

ここで、重要なことは、ウソ発見機はウソをついたかどうかを確かめるものではなく、犯人しか知らない、事件内容の細部を知っているということが決め手になる言うことです。もちろん、あなたは正解がそれかを知らないので、どこにも反応は出ません。つまり、ウソ発見は犯人を見分けることも大事なのですが、無実の人が冤罪の被害にあわないようにするという大事な機能も含まれているのです。






