「あったらいいな、をカタチにする」は某製薬会社のCMとして耳にするコピーだ。
モノが溢れる以前の時代には比較的簡単に実現できたであろう。高度経済成長期を終え、欲しいモノを殆ど手に入れることが可能となった豊かな現在の社会では、「あったらいいな」をカタチにすることはどんどん難しくなっている。
インターネットの登場で人々は様々な便益を享受するようになった。何かを検索すればその傾向を分析されて、「あったらいいな」を提案してくれる広告が画面上に表示される。自分の興味がある情報が集まるという便利な反面、そうでないものに触れる機会が減ってしまう。これでは多様性を理解することから育まれる創造性を失ってしまうのではないだろうか。
オンラインショッピングは便利である。しかし、初めからお目当ての商品をキーワード検索することで、興味の無い商品やサービスとの出会いの機会を知らず知らずの間に自分で奪っているのである。つまりデジタルは便利であるが、創造性の育成に対して大きな危険性を含んでいると言えよう。
デジタルネイティブの世代はサークルに入らなくてもハッシュタグを活用し、自分が興味のある趣味や話題で同様の価値観を持つ人を簡単に、しかも効率的に探し当て、つながることを知っている。このことは同様の価値観を持つ人々と容易につながることを可能にした一方で、自分が気づいていない潜在的な価値観や、新たな価値観を持った人々との出会いの機会を奪うというトレードオフの関係にあることを意味する。
外に出てスーパーに行けば、自分が興味のなかった品物も目に入る。どんな商品が売れているのかも推測できる。
授業に出て友達と話せばインターネットで検索するより早く自分の知らない情報にたどり着くことも可能だ。
旅行に行けば初めて出会う参加者や旅先で会う人との会話や訪れた場所で見聞きすることで新たな発見を手に入れることもある。
もうすぐ秋学期が始まる。学生に改めて気づいて欲しい。インターネットは世界とつながる便利な道具である。一方で近くの人々とつながりにくくなったり、多様性を理解しにくくなる副作用があることを忘れてはいけない。
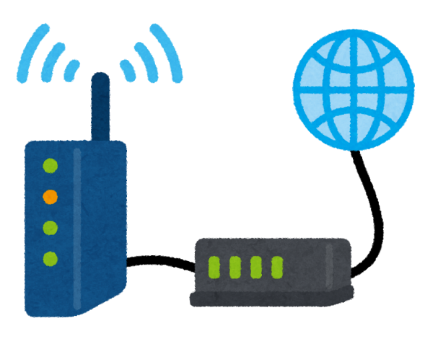

国際コミュニケーション学部 観光学科 小山 聖治
⇒ 国際コミュニケーション学部 観光学科ページ






