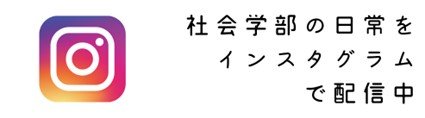社会学科データサイエンス専攻3年生は、6月1日から7月27日までの間に隔週1回、計5回の形で、ミニ版PBL学習プログラム「社会連携:多世代(地域住民×学生)協働に資するスマホ教室活用学習プログラム」に参加しました。 これは、産学連携プログラムの試みとして、関西国際大学社会学科・NTTドコモ・神戸市連携事業が共催するプログラムです。
このプログラムは、関西国際大学社会学科としても地域協働がテーマの1つで、学生達により実社会に近い形で地域課題解決に取組し、学習してもらう狙いです。データサイエンス専攻3ゼミの学生が自由参加「専門演習Ⅲ」(6月上旬~7月下旬)の枠を活用し、プログラムを組み込んで遂行しました。

社会学部3年生データサイエンス専攻の3ゼミから計26名が参加してくれました。 プログラムの内容は以下のとおりです。
| 初回 | プログラム概要説明・動機付け | グループ分けをして、コミュニケーションの基本を学ぶ |
|---|---|---|
| 2回目 | 地域住民と学生との初対面 | スマホの話題を中心に交流し、仲良くなる 高齢者の方とうまくコミュニケーションを取り、次回のスマホ教室実演に臨む |
| 3回目 | スマホ教室模擬編 スマホShop現場の方によるスマホ教室の実演 |
スマホでカメラを使おうというテーマで、カメラを使うときに気を付けることや上手に写真を撮る方法などについて、地域の高齢者にやさしく教える 最後に各グループが次回向けにおすすめアプリの提案を考える |
| 4回目 | 実践スマホ教室(学生のおすすめアプリ) | 各グループからスマホ教室で高齢者が使えるおすすめアプリを紹介 各グループのリハーサル発表を行い、神戸駅前店やNTTドコモ神戸支店から第一線で活躍するプロの方に学生の発表に対するコメント(指摘・アドバイス)をいただく 学生はスマホ教室現場のノウハウを学ぶことができる |
| 5回目 | 模擬スマホ教室の発表 | 前回のプロの方から指摘された箇所を修正し、プレゼンテーション資料をバージョンアップして、実際のスマホ教室運営の模擬発表を行う 今回は、高齢者が使いやすいアプリを紹介するだけでなく、そのアプリを使った実践的な活用方法も紹介 |
本プログラムの参加により、学生たちは、少なくとも以下の3点の意識を高めることができたと考えられます。
- 社会的孤立・孤独の予防や多様な社会的ネットワークの構築に関する課題、および高齢者のデジタルディバイドを解消することで地域や社会問題の解決に貢献することについて、実践的に意識を高めた。
- 実際のビジネス現場の様子を体感し、共同で課題解決に取り組む際の努力や高齢者とのコミュニケーションスキル、注意事項、資料作成などのノウハウを学び、ビジネス現場で必要な意識を高めた。
- NTTドコモショップ神戸支店および神戸駅前店からプログラムに参加してくださった第一線で活躍するプロの方から、作成した資料や発表に対するコメント(指摘・アドバイス)を受けることで、学生自身のプロ意識を高めた。

今回のプログラム参加により、学生は社会的ネットワークを構築し、人とのつながりを深めることやスマホ活用の方法、地域のコミュニティ活動への参加の大切さについて学びました。今後はこのカリキュラムを充実させ、次年度のサービスラーニングやPBL教育に活かしたいと思います。